連作歌篇「アカトキクタチ」改十一首
先日『ノスタルジア』を見返したせいか急に思い立ち、かつて未来誌に載った連作歌篇で製作当時からその構成に得心のいっていなかったものが先ほど改めて仕上がったので、載せておく。
初出時と比較して、主に変化したことは一首増えたことと、配列を入れ替えたことの二点。それと構成を視覚的にした。
井筒俊彦『意識と本質』を読んでいた時期に重ねてタルコフスキー『ノスタルジア』を観た。その上に朝吹真理子『流跡』を読んだ経験が、この歌群の骨格となっている。それは現れる名詞を見ていただければ明らかなことだと思う。視覚的には、岡井隆『伊太利亜』や高貝弘也の詩篇から受けた影響に負うところが大きい。

アカトキクタチ -Pray for Nostalghia- 山本千景
われらみな囚はれなればあの樹へと流れてやまず意識の水は
滑り出づる刹那あるらむ牢獄に深く繋がる四肢にありせば
流れゆく霞のごとく大らかにあるべきものを庭の五月雨
巫覡して水底ふかき行くすゑの水面に映る水月まどか
しづみゆくしづくしづかにいづくにか咲きにほふらむ蓮のありけむ
あらずあらず移ろふもののただなかに置かれたるのみゆゑに写し絵
本質は花とあらはれそれさへもすでに鏡のなかに古びて
月も日も神のあらはれ。御仏の降臨にしてそれかあらぬか
手遊びの果てに到りつぬばたまの闇より溶けし霧にひたされ
死後の世に賜ふ手形はひさかたの日こそ我らが棲み処と証せ
かたわれに逢ふこともなきかはたれを向うの岸にいまはたそがれ
ルビ:巫覡(ふげき)
ツイキャスにて朗読を行いました。録画を置いておきます。
https://twitcasting.tv/nostalfire_/movie/571390010
感想、引用、お待ちしております。
沙羅みなみ『日時計』(青磁社)に寄せて

そうしなくてよかったのかはわからない。光は、けれど時おりそよぐ
高貝弘也の詩集を六冊読んだ。更に一冊頼んだ。それはさておき、もう随分前から現代短歌最大の収穫として最も推していながら、いまだに読み終えていなかった一冊をようやく読み終えた。
それが、冒頭に掲げた一首に始まる歌集『日時計』だ。
沙羅みなみの手になり青磁社より刊行されたこの歌集は、現代詩への傾斜を帯びた短歌が示すひとつの極北星として燦爛たる光彩を放っている。
今回はそんな歌集を評してゆきたい。
沙羅は、岡井隆がまだ未来短歌会において自らの手で選歌欄を受け持っていたときの会員で、岡井の選歌欄「曲がれる谿の雅歌」に所属していたようだ。恐らくはこの歌集の出版と評価を機に、無選歌欄「ニューアトランティス」に移動したのだろう。そのあたりのことはあとがきに詳述されている。
章立てとしては〈0〉5篇〈Ⅰ〉26篇〈Ⅱ〉26篇〈Ⅲ〉18篇に、跋文(岡井隆)と著者あとがきが付されている形だ。
なお、冒頭に引用した一首は章に組み込まれておらず、歌集の初めに独立して置かれている。そのため、初読の時点において件の一首は歌集への詞書のようにも受け取れることを附記しておく。
さて、ようやく本題だ。まず沙羅の短歌と現代詩の架橋線として、/〈スラッシュ〉と()〈パーレン〉、そして句読点の多用を挙げていきたい。多用といっても歌集としては、という話だが。
その前に著者の身体感覚を紐解く鍵になる三首の歌群を挙げておく。0章冒頭を飾る「降りつもる」というこの歌群については岡井隆も跋文で言及しているものだが、だからこそ以下に引いておく。
しんしんと時間がしろく降りつもりやがて消えゆくまでを見ていた
過去の記憶に深く埋もれたる匂いの影のよぎるような日
そうであることとそうではないことの間はつねに淡く隔たる
ルビ=過去(すぎゆき)、間(あわい)
作者のスラッシュに対する感覚がそのまま歌としての形を得た、そんな気さえしてしまう。一首目では四句から結句にかけての句跨りを介しつつ時間としての雪の明滅をいい、二首目で現前しないものの残滓を視覚によらない体言の連鎖によって示す。
特に三首目に感覚は顕著であり、隔たるという動詞の持つ中動性が見事に形象化している。現代語としては一語に見えるが、これは古語的観点から見れば〈隔つ〉に受身・自発の〈る〉が付属して一語になったものだ。
あえて言えば、「己の意志や力とは無関係に隔てられる」ということになるだろう。これは受動態のように見えるが中動態なのであり、直前に「淡く」という形容がなされているのも、おそらくそのためだ。己の意志でないものを明確に知覚することは不可能といっていい。日本語における古語感覚の揺曳は、こういうところに見え隠れする。
……のっけから話が随分逸れてしまった。要するに、長いようで短いようでもある飛躍的な時間感覚と、記憶や認識の境界における曖昧な断続性が詠われているということだ。
・逆転をもたらすスラッシュ
その場所へ行こうとするが入口はすでに/未だに閉ざされている P.51
それ以上くるしまぬよう封印をしたのに/したので色あざやかだ P.62
そうでなければ会うはずのない人だったけれど出会った/だから出会った P.99
これ以上近くならない/これ以上遠くならない/ようにあかるさ P.175
四首ともにスラッシュの前と後とで視座がまるで入れ替わっており、スラッシュの後で変えられた言い回しが異様なまでの事実性、現実味を帯びている。
なかでも特筆すべきは一首目の副詞の効果だ。現象が既定したとき、その時点でもう物事は継続性を帯びており、人が必ずしも一つの時間軸にのみ立っているのではないことに気づかされる。この時間の飛躍は通常の詠い方ではなかなか起こらない稀有な例であり、スラッシュならではの技といえる。
いちどきに隔たった時間軸に立つ歌ということで即座に思い出すのは、かの藤原良経の詠んだ〈見ぬ世まで思ひのこさぬ眺めよりむかしに霞む春のあけぼの〉ぐらいで、そう類例に富んだものではないと思われる。
こういった歌は過去回想とはその性質をまったく異にするが、見ての通り良経公の詠歌は日本語にかなりの圧縮がかかっており、古典だからという話はさておいて浸透力では沙羅の作のほうに軍配が挙がる。中世和歌の顰に倣っていえば、文体で「もみもみと」せずとも歌を曲折に富んだものになしえるわけで、ここは現代人の面目躍如といったところか。
・前景化するパーレン
(裏庭に生えているのは耳ざとい樹だと気づいたように)不安だ P.76
(もう一度ここへ戻って来るなんて)白い小部屋はいくつか増えて P.114
ぬばたまの(死んだのは誰)冥き水流れる(わたし)夢のまにまに P.135
海がよく見えるのだからこの海を眺めていようと思う(日がある) P.202
四首とも心象や独白、感受による侵食が見て取れるだろう。パーレンで括られた副次的な部分がかえって前景化してきており、日常における違和や乖離の切り取りが鮮やかだ。ただ、三首目については収録されている連作の構成上おそらく月経を背景に詠まれたものだと考えている。また、四首目のパーレンが面白い効果を挙げているのが見逃せない。
日がある、というのは順当に考えれば連体修飾でそういう一日が巡ってくることへの安らぎなのだが、パーレンでくくられたことで終止形で止められているようにも見える。
その結果、歌の趣は「そこに太陽が実在していることの再確認」といった様相を帯びている。上の句について、日がまともに出ていなければ海をよく見通すことは難しい。そう思い合わせたとき、海も日も現実のそれらであると同時に、形象としての輝きをその身に纏って見えはしないだろうか。
・語りとしての句読点
十六時。あらゆるものの輪郭がするどさを増すそんな時刻だ P.58
行ったのに帰ろうとして、刺草はだから鋭く触れたのだろう P.92
銀色の時計なくした。体内の時間軸みなくるい始めた P.102
ふかく病む。その深さゆえまわりにはすこやかなものばかり集まる P.128
句読点以前が場面設定、状況説明の役割を担っている。小説から抜き出された一文であるかのような雰囲気に、他人事ではない気分に襲われる技法だと思う。句読点の持つたゆたいに、歌の滞空時間は延長され、臨場感が倍増する。その結果、歌において読者にゆだねられた主体性は加速する。
・文節を無視した句跨り/句割れ
立ち止まるまでもない景だったがかすかな違和はけどもあった P.65
しあわせな死者やふしあわせな死者があちらこちらにあふれては 春 P.68
さやさやと中心を蝕まれゆく飼いならしつつある錯覚に P.132
ルビ=景(ひかり)
句跨りは塚本邦雄によって大成された修辞技法だが、多く下の句で行われるものであり、文節や音節に従って言葉を千切ることによって意味を削いだり暴力性を生んだりするものだったが、平成令和の短歌にはそこから遊離した句跨り・句割れが多くみられる。
沙羅の歌にもその影は窺えるが、どうも前衛と現在のあいだで、内容との相乗効果を失っていない感じを受けた。律読法に則ればそれぞれ上の句が、
たちどまる/までもないひか/りだったが
しあわせな/ししゃやふしあわ/せなししゃが
さやさやと/ちゅうしんをむし/ばまれゆく
といった風に言葉の切断が起こっていることは明らかだ。
塚本以後を生きる我々は歌人それぞれの作品の中でさえ含みを持たせた句跨りと単なるリズムとしての句跨りが混在しているわけだが、沙羅の作品では歌の内容とこの文節を無視した句跨りに一定の呼応関係が見受けられるというのは私の穿ちすぎだろうか。
・岡井調について
岡井隆の直弟子ということになるので、影響関係についても軽く触れておく。
ひとつずつ積み上げて来たつもりだが崩れるときは一瞬で、いい P.56
→上の句の言い回し、特に「来た」が漢字であること
いつまでもみつけてもらえぬかくれんぼほんとはだれが鬼だったのか P.60
→革命にむかふ青春のあをい花ほんとに咲いてゐたんだつてば/岡井隆『大洪水の前の晴天』
みずいろの薬の効いてくるまでを目をあけているうすぐらいので P.67
→理由になっているのかいないのかわからない「ので」の使い方。
感情をたたみ直してゆくような一日だった 夕暮が来る P.116
→夕暮れが質量を伴っていきなり訪れるあたりのドラマ性が岡井的。
加速度がついているから止まれない走りたかったわけではないが P.141
→かけた梯子をすぐに外すのが理屈を下の句で煙に巻くのが巧いので。
・端的に列挙しておく秀歌
時の輪の廻りはるかにその手より失われゆく青のしずけさ 廻り=めぐり P.79
もし花束として受けとっていたならば 日の射す径に野あざみは咲く P.81
まぼろしの海を見ている夕まぐれアールグレイの葉のひらくまで P.90
かなしみは憎しみという石になりそれはわずかな違いだったが P.93
もうずっと前に花火は尽きていた 僕は自分を燃やしつづけた P.107
いくたびか話は途切れそのうちに雨はふたたび降り出していた P.115
椅子があり光があってその部屋にいてよいのかはわからなかった P.139
そうでなかった昨日は遠くかなしみが咲かせたような一輪だった P.180
ひとたびは傾けていい断崖へ水のこぼれるその角度まで P.184断崖=きりぎし
夕やみの近づいてくる足元をつめたい影がふかく浸した P.194
しばらくを集まりやがて散る雲の光をしんとあびてあかるさ P.197
三首目→夕まぐれアールグレイ葉のひらくまで、韻律が秀抜。幻視の安らぎ。
四首目→しみ、しみ、石(意志、意思)。これは韻律に加えて連想の妙。
七首目→設えられていることへの不安感。
八首目→「遠く」で切ってもいいが、あえて切らずに昨日という日が一輪の花であったと受け取ってみるのも悪くない。
——閑話休題——
さて、書くべきことはあらかた書き尽くし、この長ったらしい歌集評もいいかげん佳境に差し掛かってきた。この『日時計』が二首のペアと三首のトリオで多くを構成されている歌集だということは岡井隆の跋文に詳しい。更に、著者のあとがきではこの歌集は「物語」という位置づけであることが窺える。
しかし、ここはひとつ筆者なりの取り組みとして特に優れていると感じた八首による一篇を連作として読んでみたい。いましばらくのお付き合いを。
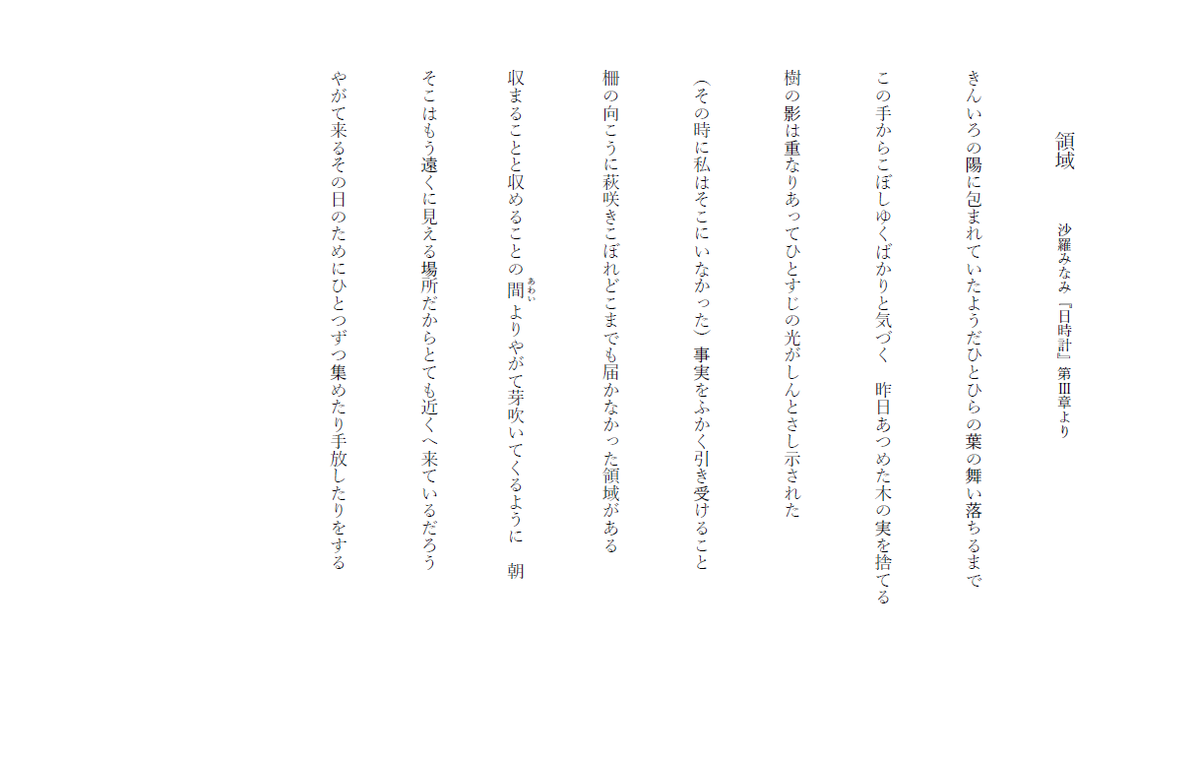
領域 沙羅みなみ『日時計』第Ⅲ章より
きんいろの陽に包まれていたようだひとひらの葉の舞い落ちるまで
この手からこぼしゆくばかりと気づく 昨日あつめた木の実を捨てる
樹の影は重なりあってひとすじの光がしんとさし示された
(その時に私はそこにいなかった)事実をふかく引き受けること
柵の向こうに萩咲きこぼれどこまでも届かなかった領域がある
収まることと収めることの間(あわい)よりやがて芽吹いてくるように 朝
そこはもう遠くに見える場所だからとても近くへ来ているだろう
やがて来るその日のためにひとつずつ集めたり手放したりをする
この歌集には三首ほどリルケの「秋」を思わせる歌が出てくるが、これもその一首だ。面白いことに、陽射しに染まる葉を詠んでいるようでそうでもない。
ここで金色の陽に包まれているのは、作中主体=読者である私に他ならない。そして私は二首目で気づいてしまう。昨日集めた木の実を、これまで蓄積してきた感情を、今は捨て去る。道が示される。光の道が。木の実と感情を捨ててもたらされた影によって。それは、すべて判断や決断において確固たる「私」がいたことなど一度もなかった、そう思い定めて初めて見えてくる道だった。
いま、柵の向こうには零れんばかりの萩の花が咲いている。しかしそれは今まで届くことのなかった領域のように遠く見えた。朝。
収めたのではない、収まったのでもない、朝。それは芽吹いて。
遠く見えた/それは遠くに見えていた。昨日集めた木の実を捨て去る前はまだ見えてもいなかったあの場所が、いまはたしかにこの目に映っている。金色の陽差しに包まれて——あれは何だろう。いままでに集めては手放したものの数々が、光を帯びて。
いつか来るだろうその日は、無限の肯定に満ちて。
私を暖かく照らしている。
通読有難うございました。似ても似つかないと言われそうですが、沙羅さんの歌風は私にとって澪標のようなものです。
それでは、また次の記事で。
Am I Highly Sensitive Person?
HSS型HSPという概念を知り、自らの相剋と矛盾に満ちた特性に合点が行きそうな気がしている。
— 流霞 (@Nostalfire_) 2019年9月23日
ADHDとは違ったということか。薬が要るという衝迫は今のところない。仕事で変わったことを要求されることがないからかもしれない。
秋の空気を浴びて以来、どちらかといえば静かに鈍く研ぎ澄まされている。
さっき程度について引っかかった設問を答え直したら案の定スコアが上がった。
— 流霞 (@Nostalfire_) 2019年9月23日
『#HSP診断テスト - 選ぶだけの簡単セルフチェック』 https://t.co/3ltF5qOm9U #HSP
HSP(Highly Sensitive Person)という特性を知った。予てから疑っているADHD特性の有無は未だわかっていないままだが、むしろこのHSPこそが虚無感、徒労感、躁鬱感の正体だったのではないかと考えている。
また、国語ばかりが得意であったこと、いちいち日本語の語源に遡行する趣味を持つこと、これらの特性を鑑みてもどうやら自分がHSPであることは確実な気がしている。
しかし、プライベートにおいて遅刻癖のあることと片付けが絶望的に不得手なこと、忘れ物/物忘れの多さ激しさを鑑みるに、自分がADHDであるのではないかという疑念は晴れない。
幼少期、母を悩ませた特性のうち最も顕著なものに、「靴下の縫い目と衣服のブランドタグ/洗濯タグを激烈に嫌う、特に後者は切り取る」ということがあり、その裏返しとして現在は酒器や食器に格別の思い入れと愛着を持つような特性を得た、とも考えられなくはない。
このうち前者は、ADHDの子供が持つ特性のひとつであるようだ。それにしても、父親に与えられた名前にこれほど縛られるとは、と日々思う。混じり気のない、という意味だ。
高貝弘也の『白緑』にある「授粉」という詩に、
そら いのちを命づけて
ただ言葉には出さないで
※命に〈な〉のルビ
という一節があるが、名前をつけるというのは本当に恐ろしい行為だと思う。そのあたりは、映画『ゲド戦記』を観た当時からずっと考えていることだ。
最近精神が悪くなってもどうにか救われているのは、朝吹真理子の『TIMELESS』を通してThe Durutti Columnの音楽、ひいてはVini Reillyという存在に出会ったことが極めて大きい。どこまで神経が尖ろうが擦り減ろうが初夏の陽射しを浴びられるため、内面に余裕が出来た。
そういう時間の合間に東山魁夷の絵を眺める。愛用の器やグラスで酒を飲む。それで大抵の闇を押し流すことが出来ている。
これからも美の享受者として死なずに生きてゆきたいものだ。そしてその美を、歌という器によって媒介せねばならない。世界に向けて。
無月流霞抄・壱「落葉の風」
Twitter上で、即詠流霞と称するハッシュタグを用いたライブ即詠をもう随分長いあいだ試みている。先日行ったものの出来が良いように思われるため、細部に手を入れた上でまとまった歌群〈無月流霞抄〉として公開することにした。
なお、即詠流霞については詠み出した順序を意識の流れとして重視したいため、普段の連作歌篇のように配列に作為を加えることは一切行わなかった。収録しなかった歌がいくつかあり、多少の推敲を試みたのみであることを言明しておく。コメント欄やTwitterのDMによる感想は歓迎致します。
追記:ツイキャスで朗読を行いました。録画しています。
https://twitcasting.tv/nostalfire_/movie/568757521
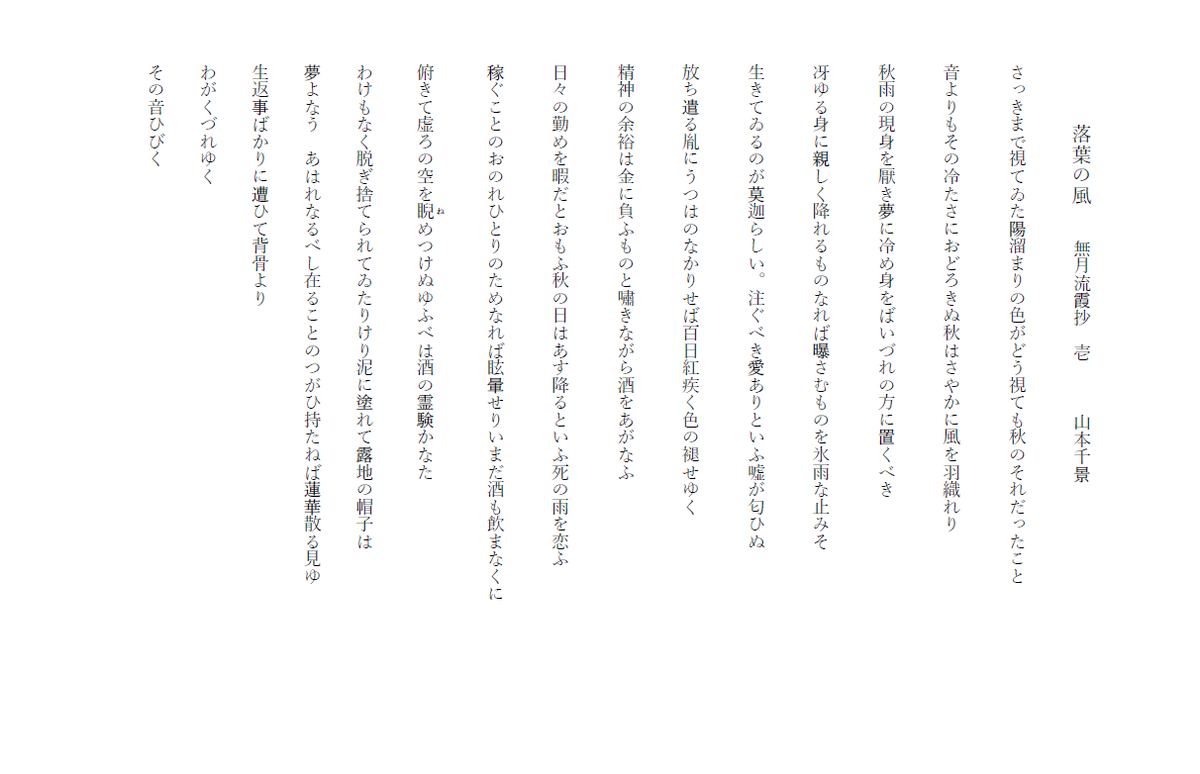



落葉の風 無月流霞抄〈壱〉 山本千景
さつきまで視てゐた陽溜まりの色がどう視ても秋のそれだつたこと
音よりもその冷たさにおどろきぬ秋はさやかに風を羽織れり
秋雨の現身を厭き夢に冷め身をばいづれの方に置くべき
冴ゆる身に親しく降れるものなれば曝さむものを氷雨な止みそ
生きてゐるのが莫迦らしい。注ぐべき愛ありといふ嘘が匂ひぬ
放ち遣る胤にうつはのなかりせば百日紅疾く色の褪せゆく
精神の余裕は金に負ふものと嘯きながら酒をあがなふ
日々の勤めを暇だとおもふ秋の日はあす降るといふ死の雨を恋ふ
稼ぐことのおのれひとりのためなれば眩暈せりいまだ酒も飲まなくに
俯きて虚ろの空を睨めつけぬゆふべは酒の霊験かなた
わけもなく脱ぎ捨てられてゐたりけり泥に塗れて露地の帽子は
夢よなう あはれなるべし在ることのつがひ持たねば蓮華散る見ゆ
生返事ばかりに遭ひて背骨より
わがくづれゆく
その音ひびく
不真面目となりにけるかな!
替への利く
歯車とのみ我を思へば——
あすを励んだところで取りかへせないので辞めるか死ぬか里に帰るか
ピストルが手元にあれば
今すぐに——
顳顬を撃ち畢らむものを!
喰ひ気味の「はい」に疲れて死にさうだ。俺の話に値打ちあらずも
ものなべて拒否に見え来る秋の夜を木の葉となりて降るすべもがも
終はらざる鬱憂あればいにしへゆ歌の碇は重石となりぬ
吐きさうだ。指の震へが止まらない。蝉の骸を柩とおもふ
死なせよといふ内圧の高まりに
包丁を持つ
持つだけは持つ
掟つべしまた鎧ふべしあはれあはれ生まれ来し日のままの脆弱
うちつけに頭(づ)をうちつけてそのままに眠れ今宵を疾く遣り過ごせ
人みなの
語らふこゑも金属の
打ちあふ音としか聴こえ来ず
くづおれてレジ締めを投げ出しにけり監視カメラが夜をひらめく
目に映るすべてのものを蹴飛ばした。なにも起きない心の奥に。
取り落とす鍵のうるささ。期せずしてわれがわたしの死に目に遭ひぬ
さつきから喉が渇いて仕方なく仕方なく飲むことが愉快だ
やけくそに飲むハイネケンやけくそに喰らふファミチキ 死ぬ気ゼロだな
秋風のさなかに呷るハイネケン。辛いなあ今はそれがいとしい
ガジュマルにとつての水がさしあたり僕にはHeinekenだらう Vie.
終電をいつそ逃してしまひなばあすはますます滅茶苦茶ならむ
死神の予告のやうに吹いてきた手首に絡む風が痛いや
OJT, ヴィジョン、面談、隣なる座席ゆ届くことのはに醒め
聖杯のごとくかがやく空き缶のおかはりはつか迷ひてゐたり
頭だけは下げて帰らう職業に貴賤あるとか俺は知らねえ
法師蝉ゆるびてゐたなさういへば。俺がしんどいのも無理はない
放送禁止用語を入れて歌を詠む、爆破みたいな真似がしたいな
さう俺は、生まれが左利きなので左手だけでプルタブが開く
無頼だ、無頼。おまへら死んでねえんだよ。死にながら詠んだ歌が飲みたい
どん底の底の底から這ひあがる、俺は不死鳥。いまに見さらせ。
緑色の上着を着ながら緑色のHaineken飲む俺は樹木か
どう見ても俺は不審者。モンエナのやうにハイネケンを飲んでる
どうせなら瓶で飲みたかつたけどしやあねえ、缶で許してやんよ
手に残る麦酒のかをり、それはさう。すこしぐらゐは度を過ごさうぜ
目のまへで立ち止まりつるをとこあり。こはいなあおまへ誰の使者だよ
気違ひと言はれてもいい、それこそが俺のすべてと頭を下げにけり
君たちは莫迦といふかもしれないが雛罌粟の咲く丘で待つてる
立ち上ぐる世界かなしゑ訝しゑ歌に満ちゆく嘘の香が Vie.
要するに桁はづれだといふことさ。翳りのなかにひかりが淡い
目に映るすべてが敵だ。共鳴りの果てに移ろふ私を視留む
寝ねざれば心研がれてゐたりけり鉛筆の芯は紙へと尖る
モイ!iPhoneとVAIOからキャス配信中!!
一度アカウントを破壊したりもあったのですが、Twitterを媒介にツイキャスというライブアプリを利用しており、近況の報告やその時々の詩文に纏わる思索の放送に用いております。
人間ができていないので話のネタもないのに放送するという莫迦をやるのはもうやめるつもりでいますが、その分内容のあることをお話して参る所存です。宜しければお付き合いくださいませ。
念のため、神戸の出身ですのでやや柄の悪い関西弁となっておりますことをご了承ください。
昨晩(というか昨々晩)のキャス×3枠ですが、まともなことを面白可笑しく喋ることができたという自負のもと完全に録画が残るように致しました。「詩文について/高貝弘也など」というタイトルで、現代詩における余白の効果と短歌連作の在り方について語っています。
— 流霞 (@Nostalfire_) 2019年9月21日
お聴きいただけましたら幸いです。 https://t.co/aY5nspt66T
https://twitcasting.tv/nostalfire_
私が現代語で歌を詠まない理由
Twitterで、こんなことを書いていました。
私が完全に現代語で短歌をやらない理由について、近々ブログを書きます。
とてもくだらないことです。いまは未来で最も尊敬している沙羅みなみを読んでいます。
というわけで、とてもくだらないことです。
現代かなづかいと現代語を私が歌作において主軸に据えてこなかったのは、偏にその解禁が古典和歌への断絶をもたらすと考えていたからです。断絶をもたらすというと短歌の総体的な問題として、と聞こえるでしょうが、今回お話しするのはもっと個人的な領域のことです。
以前書いた記事に、和歌はその調べ自体が呼吸を持っており、書家が文字を連綿させているというよりは歌が始めから連綿しており、書家の筆蹟はそれの反照であり反響であるに過ぎないというようなことを記しました。
そのような感じで、自分の詠歌が古典かなづかいで古典語であることを古典共同体への大きな立脚点だと認識していたわけです。現代語を解禁することによって実人生が歌に反映する度合いが上がってしまうことも自ら嫌うところでした。歌を、自分という人間に根差した体験の記録だとか、思考の表出だという風に捉えたくないというのは、いまでもそうです。
さっきから過去形ばかりを用いているのは、私の思惟がもうすでに次のフェイズにさしかかっているために、現在形で書き留めるのが難しいことを示しています。話が回りくどくていけない。最近、高貝弘也の詩集を精読しているのですが、それで、古典共同体への接続は必ずしも仮名遣いや古典語の使用に拠らず、それ以外の方法によっても可能だという境地に、いまさら至りつつあります。
さて、では今すぐ古典語を排して現代かなづかいで歌作ができるかというと、やはりそうもいかないらしいのです。ここがどうやら矜持の介入してくるポイントで、古典かなづかいでなければ十二分に古典語としての風情を発揮しない語彙というものがあります。曰く「あはひ」曰く「にほふ」、このあたりの語彙が持つ古典的情趣を現代かなづかいで出すことは難しく、さらにこれらを現代語のなかにいきなり放り込んでなお歌に均整のとれた姿を保つことは至難を極めるでしょう。そして、歌の古典かなづかいにはまだ遣り残したことがあるのではないかという賢者めいた錯覚もあります。
それら諸々の事情というか思い込みによって、古典かなづかいを手放すことは私にとってまだ難しいようです。そういいながら、自分の詩論のすべてが荒唐無稽で支離滅裂で傍若無人なものに過ぎないという徒労感に苛まれているので、これは単なる駄文です。こんなことが書きたかったのかどうかも定かではありませんので、悪しからず。
古川日出男『ゴッド・スター』を読み終えて
ここ数日、感情も思惟もどうしようもない。まるでまとまりを持たない。泥のようだ。Twitterを普通に使うのをやめた。人を傷つけるから。誰かを呪うために言葉を吐くことに、疑問を持たなくなったから。嫌い、という感情にだけ支配されつつあったから。潰す、という目的にしか価値を見出さなくなりつつあったから。Instagramやはてなブログの更新が自動的にツイートされるような、そんな間接的な活用に留められたら、と今は思っている。主宰していた文芸批評会のアカウントも、消した。
始めから私は誰にも求められていなかった。私にしても、実は誰も求めていなったのだろうとに今にして思う。柄じゃなかった、そういうことにしておく。
自分がリアルタイムで言葉を並べるべき人間ではないということ。
いつからか、サラマンドラに
なっていた。
みんなみーんな燃えてしまった。
そんな歌を詠んだのはそう遠い話でもない。こう詠んでみたところで、世界はそうたやすく燃えてくれない。自分が燃え尽きるほうが話が早い、どんな意味合いにおいても。The Durutti Column「Vini Reilly」を聴いていたところ、哀しみのあまり何かしら書きたくなった。それでいまこれを書いている。
前回の記事への目に見える反響があまりに少なかったので以前にも増して失望している。己の内面の氷を切り裂いて記した散文なんてものは流行らない、そんな気分に苛まれている。早計だとは思うが。というか、皆もっと苦しめ。
それはそれとして、久々に小説を通読した。新潮文庫から出ている、古川日出男の『ゴッド・スター』というものだ。タイトルに惹かれた。黒田潔という方による、表紙の装画が気に入った。書籍のほうから語りかけられるのは久々だったので、嬉しかった。

私はたしかに少年の母だった。紛れもなく、「あたし」であった。途中までは文体の携えた疾走感に喰らいついていけていたが、中盤、「メージ」なる存在が現れたあたりから思考が混濁して上滑りの読書と化していたような気もする。質的には朝吹真理子『流跡』のような、散文詩に近い読後感だった。文体としてはそこに森博嗣『スカイ・クロラ』のようなドライブ感と同『クレイドゥ・ザ・スカイ』における自己乖離感が乗るような、そんな感じだった。
違う。違うの。こんな語りではあの作品の魅力を語りつくすことなんてできやしない。あたしは速度を上げる。何の?思考ってゆうか、語りの。あたしをさっきまで取り巻いていた言葉の速度に合わせて。あたしは深入りしない。内面の速度を外界のスピードに合わせて。シンプルに。あたしは彼の記憶を辿る。
とまあ、こんな文体で謎を残したまま駆け抜けていったわけだ。誰が?あたしが。あたしの感情ってゆうか、思惟が。おや、まだ残滓があったらしい。はやくここから出ないと。あたしたちは出口をさがす。出口ってどこの?
「よるです。リウカはかなしいものをみつけます。リウカにかなしいんです。それは月です。きっと月です。雲がよぎります。月がかくれます。あらわれます。かくれます。しろくなります。あさです。」
どうやら私は、とんでもない袋小路に迷い込んでしまったらしい。
![ノスタルジア [Blu-ray] ノスタルジア [Blu-ray]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51ljuY28kGL._SL160_.jpg)






